

病気で退任のティト・ビラノバ 後任はタタ・マルティーノ
2013-2014シーズンはFCバルセロナ(バルサ)にとって難しい時期だった。
このシーズン指揮をとる予定だったティト・ビラノバが、シーズン開幕を翌月に控えたタイミングで、健康上の理由で退任することになった。
有力監督は来るシーズンに向け他チームで既に契約が確定している時期だったこともあり、バルサの後任監督探しは難航した。
そんななか、当時のバルサは元パラグアイ代表監督のアルゼンチン人ヘラルド・マルティーノ(通称タタ)を候補のひとりに挙げた。
マルティーノは、2010年の南アフリカワールドカップで日本を破ったパラグアイ代表の監督を退任後、ニューウェルス・オールドボーイズ(幼少期のメッシがアルゼンチンのロサリオ在住時に所属)を率いると、低迷していたチームを蘇らせ、2013年にはニューウェルスをコパリベルタドーレス杯ベスト4、アルゼンチンリーグ優勝へと導いていた。
そして、当時のバルサ会長サンドロ・ロセイはパラグアイ大統領就任を控えていた元実業家(パラグアイで大きなシェアを誇る清涼飲料水Pulpの製造などを行う企業グループのトップだった)オラシオ・カルテスのパラグアイの邸宅で、タタ・マルティーノと接触をした。
その後候補が絞り込まれ、最終的にタタ・マルティーノが新監督の座に落ち着いた。
だが、タタ・マルティーノは2010年の南アフリカワールドカップでパラグアイ代表を率い、南米の名門クラブでも実績を出すなど監督としての評価は悪くなかったが、世界的な知名度の低さや欧州クラブでの実績不足からバルサの一部ファンの間ではタタ・マルティーノの就任は不安視されていた。
また、タタ・マルティーノとしても突然の就任で準備時間も短いなか、エゴが強い有名選手が揃うビッグクラブを指揮する難しさがあった。
かくしてシーズンは開幕し、2013年10月26日にFCバルセロナ対レアルマドリードのクラシコが開催された。
キックオフ前には、この記事冒頭写真のように「フォルサ・ティト!(がんばれ、ティト)」と闘病中のティト・ビラノバ監督に対するメッセージが観客席に表示された。
両チーム登録メンバー
スタメン:
GK :ビクトル・バルデス
DF :ダニ・アウベス、マスチェラーノ、ピケ、アドリアーノ
MF:ブスケツ、シャビ、イニエスタ
FW:セスク・ファブレガス、ネイマール、メッシ
控え:
ピント、ソング、プジョル、モントーヤ、セルジ・ロベルト
ペドロ、アレクシス・サンチェス
監督:タタ・マルティーノ
レアル・マドリード
スタメン:
GK:ディエゴ・ロペス
DF:カルバハル、ヴァラン、ペペ、マルセロ
MF:セルヒオ・ラモス、ケディラ、モドリッチ
FW: ディ・マリア、ベイル、クリスティアーノ・ロナウド
控え:
カシージャス、イジャラメンディ、アルベロア、
ヘセ、ベンゼマ、コエントラン、イスコ
監督:カルロ・アンチェロッティ
17分14秒のインダパンダンシア(独立)コール
カタルーニャを代表するバルサとスペイン中央政府を象徴すると見なされがちなレアル・マドリードには歴史的に多くの因縁があることは、既にあちこちで何度も語られている。
バルセロナがあるカタルーニャ州の人たちは、はるか何世紀も前から自分たちはスペイン人でなくカタルーニャ人であるという意識をもち、スペインからの独立を望んでいた。
だが、カタルーニャは1714年にスペイン軍に敗北すると、カタルーニャ公国としての地位と、政治的権力を失った。
20世紀にはいってもスペイン中央政府のカタルーニャに対する弾圧は続き、フランシスコ・フランコの独裁政権下では、カタルーニャ語が禁止された。
カタルーニャ人が唯一、逮捕される恐れなしに自身の感情を、カタルーニャ語で表現できたのは、カンプ・ノウでバルサの試合を観戦する時だけだった。
また、フランコ独裁政権時代には、バルサが契約を結んだはずだったアルゼンチン人アルフレッド・ディ・ステファノが、レアル・マドリードに横取りされたことも歴史的な遺恨となった。
21世紀に入ってからは、ルイス・フィーゴの件もあった。
ルイスフィーゴは、バルサのキャプテンとして先頭に立ってレアル・マドリードに立ち向かい、バルサのユニフォームを着て優勝した際にはレアルマドリードに向かって「泣き虫ブランコ(スペイン語で白の意味。レアル・マドリードのチームカラー)。チャンピオンに挨拶しろ!」と叫ぶなどバルサの象徴だったが、その後、レアル・マドリードに移籍することになり、大スキャンダルになった。
さらに、カタルーニャ人には、自分がたちが真面目に働き、積み上げた税金が、スペイン中央政府に収奪・分配された結果、お金を稼いでいない別の地方で浪費されているという不満が長年積み重なっている。
他にも幾つのも歴史的な因縁があり、スポーツと政治は別物という言葉とは裏腹に、バルサとレアルの対決は、スポーツとしてのサッカー以上の意味を持つこととなる。
2013年10月26日のクラシコでも、スペイン軍に敗北しカタルーニャが権力を失った1714年を忘れないとばかりに、前半17分14秒になると、黄色と赤のカタルーニャの旗が掲出された。
そして、カタルーニャ語でインダパンダンシア(独立の意味。スペイン語ではインデペンデンシア)のチャントが、スペイン中央政府の象徴とみなされるレアル・マドリードの目の前で鳴り響いた。

17分14秒を過ぎると、カタルーニャの旗が掲出され、インダパンダンシア・コールが鳴り響いた
ちなみに、自分は、上述のような歴史的背景を踏まえ、また、カタルーニャでは現代の若い世代でも本気でスペイン中央政府への対抗心を持っている人が多いことなど理解しつつも、スポーツとしてバルサを応援しようというスタンスを以前から持っている。
はじめてクラシコを観戦した2013年の10月も、自分は、カタルーニャの人たちの意図を理解しつつ、サッカーにおける重要な一戦として試合を見ようと心掛けた。
試合は2-1でバルサが勝利
試合終了後、自分の近くで観戦していたレアル会長のフロレンティーノ・ペレスのほうに目をやると、レアルの敗戦にも「こんな日もあるさ」という雰囲気で、冷静な表情を崩さず席を立ちスタジアム内へと消えていった。
やりたいことは、できるうちに
月並みな言い方だが、クラシコを観に行って良かったと思う。
それなりに出費はあったが、目的のために他の出費を抑えながら資金を確保できた。
クラシコ観戦当時は独身だったから、クラシコ観戦後は、「出費に見合う価値があった。一生に一度の体験ができた」と純粋に思えた。
自分はその後結婚し、家庭を持った。
そんな今、「再びクラシコを観に行くぜ!」と自信をもって言えない自分がいる。
コロナが明けても、自分はスペイン方面の出張は無いという状況だ。
そんななか、妻子を置いて自分一人だけスペインに行こうとは思えず、また、家族全員でスペイン旅行となると莫大な費用がかかり、それを捻出する金銭的な余裕はない。
そう考えると、まだ独身で状況的にも可能だった2013年にクラシコを観に行っておいてよかったと思う。
次回でいいやと考えているうちに機会を失う可能性があることを考えると、やれることはやれるうちにやっておいた方がいいなとつくづく思った。
バルサ対レアルを見ることは、自分にとって死ぬまでにやっておきたいことリストのひとつだった。
それを実現できたから、年老いたあと「ああ、人生で一度くらい、FCバルセロナとレアルマドリードの試合を現地で見たかったなあ」と嘆くことはない。
海外でワールドカップを現地観戦する、というのも死ぬまでにやっておきたいことリストのひとつだったが、これもブラジルで実現できた。
ただ、リストの未達成項目には、「アルゼンチンのボカ・ジュニオルス対リーベル・プレートのスーペル・クラシコをボンボネーラで見る」というのが残っている。
(ボンボネーラでボカの試合を何度か見たが、リーベルとのスーペルクラシコはまだ見たことがない)
容易ではないが、コロナが明ければ南米方面に海外出張が入る可能性はあるし、いつか実現させたいと思う。

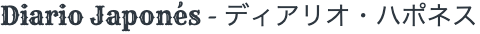



コメント